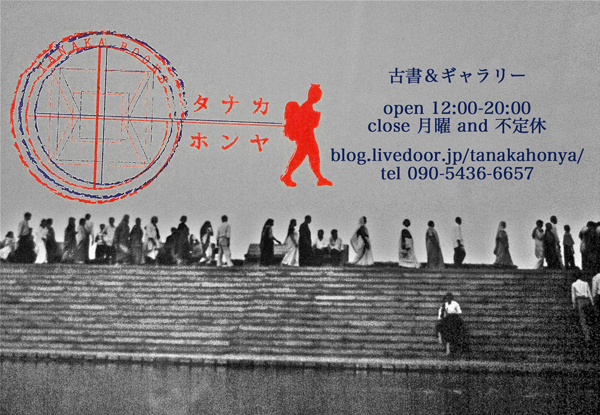昨今、日記本が流行っているというのは、出版の世界ではよく知られるところではないだろうか。商業出版でもリトルプレスでもつぎつぎと日記本が刊行されている。
僕が日記で真っ先に思い付くのが、画家のパウル・クレーの日記や全集に入っているフランツ・カフカの日記だ。国内ならやはり武田百合子の『富士日記』は外せない。このあたりは影響を受けている作家も多いはずだ。読書に関する日記だと阿久津隆『読書の日記』や柿内正午『プルーストを読む生活』がすばらしい。この二冊からより読書の幅が広がった。リトルプレスだと武塙麻衣子『諸般の事情』を偏愛している。あまりに良いので自分のつくるリトルプレスの往復書簡本に声をかけさせてもらった。
今年読んで一番面白かったのは早乙女ぐりこ『東京一人酒日記』だった。破天荒な内容だがそれをまとめる文章力に惹かれる。というように、ここには書ききれないくらい様々な日記があるわけだが、今回、紹介する吉祥寺の「古書 防破堤」店主、堤雄一「防破堤日記」ほど我が身に引き寄せて刺さってきた内容の日記はなかなかない。
ただこの作品は「日記」とあるが、日付が入っていないので厳密に定義すると、流行っている日記本の分類には属さないかもしれない。実際、読み心地も日記より随筆、もっと言うとずしんと腹にくるような重い私小説の読みごたえなのだ。
重さの理由は内容ももちろんあるが、近代文学の流れも感じさせる重厚な文章も起因している。だが重いだけじゃなく読み物として非常に魅力がある。本作には笑いの要素があるわけじゃないが、西村賢太の作品を読んでいる時のような感覚におちいった。私小説で書かれる現実のうまくいかなさからくる内面の吐露以上に、けっきょく、書き手の行動が好きなもの、信じるもののを拠り所にして、苦境を上回る強さに心をうたれる(西村賢太でいえば藤澤清造であり、本作では古書 防破堤がそれにあたるだろう)。
本作が載っている『アラザル vol.14』の冒頭に寄稿している佐々木敦が「古書 防破堤」の名付け親で、「波」でなく「破」の当て字になっている(この辺りのことも本作に書かれている)が、日々の経営や家族の健康などの苦労の中でも揺るぎなく一本筋が通っているあたりが、見事に名は体を表している屋号といえるのではなかろうか。
また、本作を魅力的にしているのは、本屋の開業や経営について細かく金銭面についてまでしっかりと書き込んでいるからだ。細部を徹底的に書いているからこそここには嘘のない切実さがある。むろん、過去の回想をベースに書いている以上、すべてが本当かどうかは読者にはわからないし、書き手が取捨選択をしていることは十分にありえる。すべての日記や随筆、私小説がそうであるように。しかし、この文章は清々しいまでに嘘がないと感じられる。
二〇二〇年の一月に開業し、まもなくすぐにコロナ禍にみまわれ、けっして楽ではない日々の記述。序盤に新刊書店ではなく古本屋を選んだ理由が父親の経営がうまくいかなかったからだと書かれているが、本当に本屋とは新刊にしろ古本にしろむずかしい商売なのだと改めて考えさせられた。
私事になるが、僕はいま、水道橋に古本屋をつくっている最中だ。本屋をやるにあたって考えれば考えるほどに、本を売ること以外の作家業や出版業で補填するしかないという考えに行きつく。それでも無理なら他の仕事をしなければならないとも思う。つまり極端なことをいえば、やるまえから本屋をやるのに本を売ることに対し期待が持てないのだ。
だが、僕はこの「防破堤日記」にはどうしても心を揺さぶられる。古本屋はけっきょくのところ、古本を仕入れて古本を売るのが仕事なのだという当たり前の事実に引き戻される。世の中には、たくさんの古本屋がある。その中でも、僕は一番自分の好みに近い本が並んでいる本屋はこの吉祥寺の「防破堤」だと言い切れる。
僕も「防破堤」を拠り所にして古本屋街道を進んでいる。まだ準備の時点であり、開業すらしていない。しかし、この日記を読んだいま、心の中で何かが始まる鐘の音が鳴った気がする。読めて良かったと心から思う。
ぜひ 読書好き、古本好き、本屋好きの方に「防破堤日記」を読んでほしい。そして吉祥寺の「古書 防破堤」に足を運んでほしい、と切に願う。