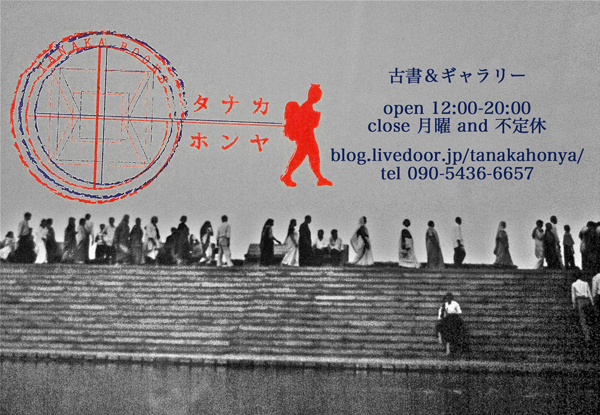『本屋さんしか行きたいとこがない』というのがこの本の題名だが、僕もよくこんな気持ちになるのでとても共感する。いろんな店に行ったり、遊ぶ場所に行ったりしたいけれど、けっきょくのところ、本屋に行きたくなる。
この本の著者は、ひとり出版社、夏葉社の島田潤一郎。ちょうど今、『あしたから出版社』がちくま文庫から文庫化されて話題になっている。さいきんの夏葉社の刊行では、万城目学のエッセイ集『万感のおもい』がある。実物を見たことがあるだろうか。H.A.Bのオンラインショップの本書に対してのコメント(本屋のオンラインショップの本の紹介の中で、個人的に随一のコメント力だと認識してるのがH.A.Bなんです)には、〈装丁は横開きで、非常に手間もかかる角丸の加工で佇まいも美しい一冊〉とある。そう、美しいのだ。そしてじつにカワイイ。手に入れて部屋の本棚に面陳したいと願うひともきっと多いんじゃなかろうか。
夏葉社の本は、本好きに愛されていると思う。読者だけでなく本屋にも。僕は今年のゴールデンウィークに岡山県倉敷市の蟲文庫に行ってきた。蟲文庫店主、田中美穂『わたしの小さな古本屋』を読んで以来、蟲文庫に行くのは念願だった。ワクワクしながら店内に入ると、本の中で読んだ古本屋の世界が広がっていた。ほとんどが古本なのかなと予想していたが、古本だけでなく新刊も置いてあった。僕は書肆侃々房から発売されたばかりの『左川ちか全集』を購入した。ここで購入したことは一生涯忘れないだろう。ゆっくり時間をかけて店内を見回したが、全ての棚の中で一番印象に残ったのが夏葉社の本だった。僕はそこでいつも東京で見慣れているはずの夏葉社の本が、またいつもと違って見えたのだ。自分の好きな本屋には夏葉社の本が並んでいることが多い。だからよく見ている。なのに、蟲文庫にある夏葉社の本はすごく魅力的で新鮮に目に映った。不思議だなあ、と思った。本は、置かれる本屋の本棚によって、ちがう姿を見せるのだ、とも思った。
『本屋さんしか行きたいとこがない』は夏葉社のなかにあるレーベル「岬書店」から刊行されている。〈夏葉社では出せないような企画を、このあたらしいレーベルの名前をつかって、すこしずつ出していきたいと思っている。〉とのことで、インディーズを意識した軽さや速さを重視した考えのレーベルのようだ。モノ・ホーミーさん(直接会ったことのある方はさん付けします)のイラストの黄色い表紙が印象的な、大阿久佳乃『のどがかわいた』も岬書店からの刊行である。詩についてのエッセイ集でこれもまたとても好きな一冊で、僕は先日、BOOKSHOP TRAVELLERで詩の棚を選書させてもらった際にこの一冊を入れた。
速さと軽さを意識しているのだろう。表紙は、講談社文芸文庫の背表紙が並ぶ本棚に、こけしのような人形が並んでいるだけの写真が印刷され、題名と著者名が書かれているだけ。カバーはなくISBNコードなく、いかにもリトルプレスという風情の本だ。この本を見て他のひとはどんなふうに思うのかわからないが、僕は夏葉社がこういう見た目がしっかりリトルプレスな本を思いきって出してくれたことがうれしかった。この本のつくりに余計なものはひとつもない。僕は常々本作りの話をする際によく話したり書いたりしているが、薄くて軽いものが好きなのだ。私家版詩集に惹かれて、いつか本屋をやってみたいと思っている理由も一つここにあるが、それはまた今度。ともかくリトルプレスをつくっている身として、心強く感じたのだ。その速さからくる無駄のなさに。
シンプルなのは中身もそうだ。ほぼほぼひたすら本屋の話。目次にはずらっと本屋の名前が並んでいる。読んでて感じるのは、本屋にしても何にしても物事を見る作者の、そのバランス感覚の良さである。ついスレた読書好きは、大型書店や独立系書店、アマゾン、とそれぞれを比較して侃々諤々してしまいがちだが、作者はそうした本屋のちがいを出版社としてのプロの目だけでなく、小さいころからの長年の読書好きの目で見てしっかり把握したそのうえで、たくさんの本屋を紹介している。だから、この作者が好きだと公言する本屋はほんとうにすばらしいのだろうなと信頼が置ける。じっさいに僕もこの本に出てくるTitleやサンブックス浜田山、BOOKS 青いカバなどは大好きだ。二〇一五年の池袋リブロ本店がなくなった話の直球の言葉には、同じくリブロに通い続けていた者としてひどく胸をうたれた。
〈リブロ池袋本店は、人文書が充実していた。芸術書棚がかっこよかった。映画と音楽の香りがした。若者だったぼくがあこがれていたもののすべて。〉
こんなに本屋が好きなひとがいてうれしいと思うし、そんなひとが出版社をしているのだからつい応援したくなる。
また、この本にはひとつ重要な視点がある。それは本との付き合い方だ。作者は様々な本屋で本を買っては積んでいる。だけど、そのことに対し、焦っているような気配はない。一週間に一冊読了するくらいのペースだと書いているし、ちくさ正文館本店の回では、〈ぼくはこの店の詩歌の棚がわかるようになって、芸術書がわかるようになって、そうして最後には、この店の歴史の棚に並んでいる函入の本を読めるようになりたい。〉と書いている。この本を読んで理解をするのには時間がかかるというゆったりとした心構え、一週間に一冊読了できれば二〇年でトータルで千冊読めるという、この長い目で人生と読書を眺めているのも特徴だろう。
今の時代はとにかく流れが速すぎる。SNSが隆盛のこの時代では、情報が本当かどうかもわからないうちに自分のなかを通り抜けていくような感覚さえある。
〈ぼくの好きな本は、おしなべてこういうことを言う。人間は誤る。気をつけろ。過信をするな。〉
一冊一冊を読むたびに、立ち止まって考える時間があってもいいのかもしれない、とこの言葉を読んで思った。読書は自分と本との時間をかけた対話なのかもしれない、と。
そして、そんな本と出会わせてくれる場所が、すなわち、本屋なのだ。そんなら本屋に行くしかないだろう、そんな気持ちにさせてくれるのが本書である。