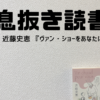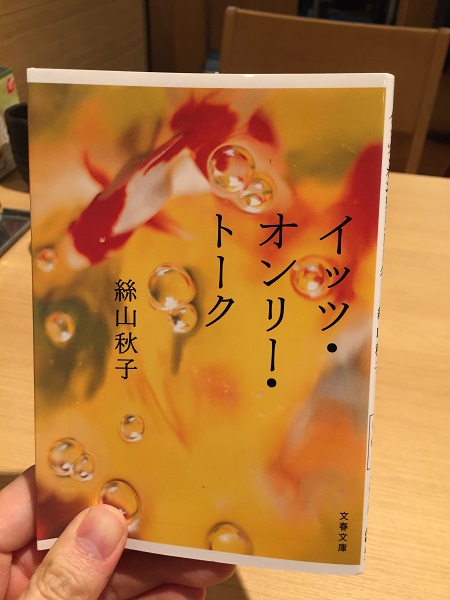近ごろ、自分の文章の好みが私小説ふうというか明確に主語が「わたし」であるものだということに思い至った。それはこの記事の通りであるし、佐々木俊尚氏の『当事者の時代』に共感するからだ。ホンシェルジュで編集として赤を入れるときに主語や目的語を注意して読むのと似ている。つまり、「誰が」「何について」書いているのかが文章においては重要で、その中で、「私が」「何かについて書いている文章」をぼくはいまのところ好んでいるということである。
そんなとき『安部公房とわたし』に出会った。
ぼくが本書と出会ったのは本が好き!のこの書評なのだが、まず装丁に惹かれた。「この美人さんは誰だろう? 安部公房の娘だろうか?」そんなことを思いながら書評や本文を読んでみると、なんと愛人ではないか。女優のことはあまり分からないのだが検索してみると『はぐれ刑事純情派スペシャル』などで見たことのある方。どんな物語が始まるのだろうと好奇心から読み始める。
自分にとって素晴らしかったことはその女優・山口果林さんの自叙伝として書かれたていることだ。その上で、感情に溺れず淡々としていながらも味わいある文体を維持している。だから、ぼくは読んでいて静かに楽しむことができた。「愛人の暴露もの」という読む前のイメージを吹き飛ばしてくれたのは嬉しい誤算だった。
安部公房について。
『R62号の発明・鉛の卵』と『砂の女』を読んだことがある程度だが、はじめて読んだ23歳のときには「こんな不穏で怖い小説を書くひとがとんな人なのだろうか」という気になった。それから7年経ち本書を読んだことでなんとなくではあるが安部公房の人となりが分かり、自分の中の謎も一部ではあるが解くことができたように思う。
世の中のアウトサイダーであり、その立ち位置から作品を紡ぎ続けた貪欲の人。それでいてカワイイ一面もある愛嬌の人。それが本書を読んでぼくが得た安部公房のイメージだ。
文体の好みと安部公房についての発見を得られた稀有な読書体験だった。