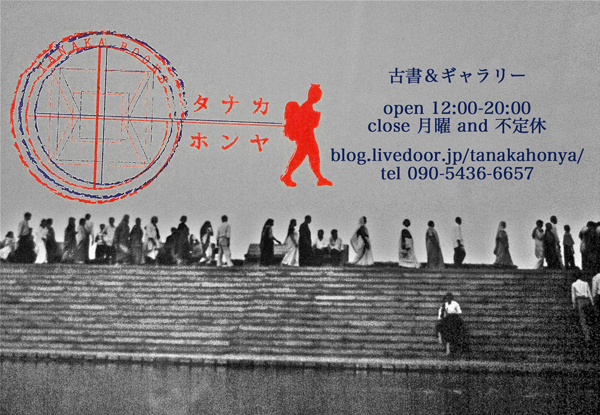猛暑の中、熱中症になってしまいヘロヘロな和氣です。みんなも気を付けて。
ってなわけで、連載「真夜中の本屋さん」も第三回目です。3回目にしてまさかの閉店の危機? という状況に僕も驚きを隠せないわけですが実際はどうなんでしょうか。真夜中の歌舞伎町で起きた実録本屋レポ。「真夜中の本屋さん 〜日本で最も危険な絵本屋、cohonの日常〜 (3)」スタートです。
***
第3話 さらば cohon、永遠に…
いきなり最終回のようなタイトルをつけてみたことには、ワケがある。
全6回中、今回で第3回目となる。編集W氏に打ち切りを宣告されたわけではないし、こちらが一方的に終わらせてしまいたいという意思表示でもない。
が、危機ではある。
小さなバーや喫茶店において、客とマスターの間に一種のジャム・セッション的な関係があるとすれば、露店商という業態はまさにフリー・ジャズそのものと言える。それもアーチー・シェップのジャズライブのように即興性が色濃く、もはや制御不能のメロディが溢れ出すことさえ常のことだ。
そしてまた、露店には壁もなければ扉もなく、バックヤードも存在しない。すべては路上に開かれた状態であり、夜の白“月”の下に晒される。この即興性と開示性こそ、露店の最大の特徴といっていいだろう。
実際、今回の“危機”は内々で収めるべきとも考えた。あるいはまた、このコラムシリーズの最終回のオチにしようかとも思っていた。
しかしながら、ハプニングにはその瞬間の熱量というものがあるだろう。ただただ時間が経つのを待ってしまえば、その熱は冷めるばかりだ。それに情報を隠匿するかのような行為も性に合わない。
熱狂のライブという溶錬炉でメロディを奏で、リズムを打ち、フリーキー・トーンで観客を沸かせるサクソフォンは、時に赤く溶解した金属の湯のような威圧感を放つことさえある。その沸騰と赤熱の絶頂こそがフリー・ジャズの本質だろう。冷めたジャズをありがたがる人間など、いるはずもない。それが、包み隠さず書くことにした経緯だ。
第3回目のテーマは、cohonとやくざである。

日付が変わり、曜日は既に土曜から日曜へと移っている。オープン作業が完了したのは、8月4日の0時30分のことだ。前の仕事が押していたためのオープンの遅延だが、あまり不機嫌ではなかった。
不思議なもので、飲食店の繁忙と閑散は地域で大まかに共通する。歌舞伎を全体としたマクロの賑わいは、当店のミクロな混み具合にも反映される可能性が高い。そして予測の通り、その日は来店のお客様が多かった。4時近い時間帯まで営業を続けた。そろそろ閉めるか、と思っていたころだ。一人の男性がふらりと近づいてきた。
「これは何だ?」
十中八九というくらいの、それはよくある質問の一つだった。過去には占い師、手品師、宗教の勧誘かと訊かれたこともある。
「絵本屋やってます。コーヒーも淹れますよ」
ふうん、と男は舐めるように店を観察し始める。無精ひげに、少しヨレた黒いスーツを着ていた。四十代半ばくらいだろうか。セカンドバッグを小脇に抱えている。
「許可が出るわけはないな」
お世辞にも清潔感がある身なりではなかったが、その言葉は単刀直入で無駄がない。そして経験上、多くの人は「こんなところで許可が出るんですか?」と尋ねてくるものだ。男のこの断定的な言い方に、ほんの少しの違和感があった。すこし返答に窮する私に対して、男が言葉を続ける。
「この街にはこの街の、歌舞伎のルールがあるのはわかるな。誰か他の人間に絡まれはしなかったか?」
「怖そうなお兄さんに『頑張れよ』って言われたことがありました」
「怖そうな、ね……」
男がにやりと笑う。いびつな並びの歯だ。ヤニのせいか、少し黄色みがかかった色をしていた。
「“悪い商売”をしてるわけじゃないのは見てわかる。悪い商売は許さないが……」
悪い商売というものが何を指すのか、その答えはもちろん一つしかないだろう。
「ここはコーヒーと絵本なんだろ? いいじゃねぇか。今回はコーヒーを頼んでやるよ。今回はな」
そうして男が少し、こちらへにじり寄った。
「次に会えばこの対応はしない」
そうして男は堰を切るように大きな声で笑い出した。無精ひげといびつな歯が大きく動くが、目だけはこちらを捉えて離さない。本心ではまったく不愉快だと言わんばかりの冷たい視線。笑い声だけが響いた。
たまたま歩いていた若い二人を、男は不躾な口調で呼び止めた。
「おい、コーヒー淹れてくれるってよ。飲んでいけよ。奢ってやる」
いいんですか、と若い二人はすぐに反応し、無邪気に喜んだ。正直なところ、私は安堵したという感覚だった。
第三者がいれば、不測の事態があっても止めに入ってくれるかもしれない、というのがその理由だ。そして少なくとも今、男はここで暴力や恐喝の沙汰を起こす気はないという意味も含ませていると思われた。とはいえ、何が引き金となって男の逆鱗に触れてしまうかは想像もつかない。実際、男の堪忍袋の尾はそう強靭なものであるようには思えなかった。
男はセカンドバッグから金を探り始めた。乱雑に詰め込まれた万札が数十枚、ともすれば百枚を超えるのではないかという数が覗く。
(あっ、これは本当にガチだわ……)
生来、呑気なわりに好奇心旺盛な性格である。その状況にあっても、その多額の現金を見るまでは気分はわりに野次馬的であった。
「おまえの名前は訊かない。連絡先も。見逃す。すべて見逃してやる。それが俺の判断だ。次はおまえがどう行動すべきか判断しろ。わかるな?」
首肯する以外の反応が他にあるわけもない。男はそう言って、歌舞伎の中心街へと消えていった。
死ぬかと思った。

「いやー、でもマジでイケてるっすよ、この店。コーヒーうまー」
コーヒーを奢られた若い二人もまた、呑気なものであった。
「それにしてもマジ怖かったっすね」
「ガチの反社会的勢力だったね……」
「これが本当の闇営業っすね」
誰がうまいこと言えと。
それはそうと、相手も相手なりの仁義は確かに切っていた。この街のルールがあることも間違いない。その上で、暴力団側に“貸し”を作ってしまった状況は極めて危うい。同じ場所で同じ営業を続けることは事実上、不可能だろう。
「この店、続けてほしいっすよ。通いますもん。本当に」
「命があと2、3個あればなぁ……」
店をたたみながら、そんな軽口をボヤいてみた。

それにしても何の予告もなく営業ができなくなってしまったこと自体はとても悔いている。上記の事情を知らずに店のオープンを待ってくれている人も、きっといるはずである。開業した店は自分の子供と同じだ。自分で生み育て、店を健やかに生かし続ける責務があるのだ。
残念ながら店の廃業を決断する場合もあるが、このときもお世話になった人たちに挨拶をして回り、丁寧に謝意を伝える。揺りかごから墓場まで、店の一生のすべてを担うことが店主としての責任であろうと思う。つまり、今の私には廃業の挨拶回りか店の存続かという選択肢が与えられていることになる。
もちろん答えは一択しかない。これですべてを諦めて終わらせることは絶対にない。そもそもやくざに脅されてあっさり廃業ということ自体が腹立たしい。何せ公園の前の土地である。さすがにやくざも「あの公園、俺のモンだかんな!」なんて幼児のような因縁をつけないだろうと思って大久保公園の前で始めたのだ。
つまり恥ずかしいのはやくざの方ではないか。それにセコい。こんか絵本屋からみかじめ料を取ろうという魂胆もみっともない。ケチくさい。ばーかばーか。お前の母ちゃn……(愚痴が止まらないので以下略)

ともかく、第4回目のコラムがどのようなものになるかは、現状まったく定まっていない。冒頭で即興性にこだわっていたのはそのせいである。cohonの在り方もコラムのざっくりとしたプロットも一旦はパァになってしまったが、どれもこれも頑張って再建し、続けていくしかないのだ。
「明日また考えよう。明日は明日の太陽がピカピカやねん!」とは小学5年生のチエちゃんの至言である(アニメ版 じゃりン子チエ 第3話より)。
コラムはつづく。cohonもつづく。