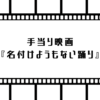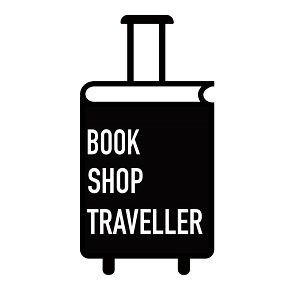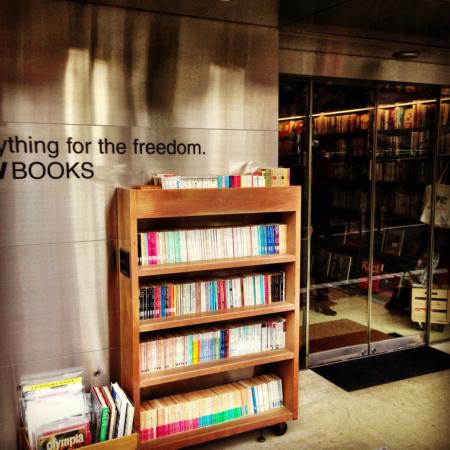遅くなりましたが明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さてさて、いつもの振り返りであります。去年はコロナ禍に続く政治のアレコレで全体感から書きましたが、まあ今回はさらに絶望が深くなったというだけでわざわざここで書くまでもないかなあと思い(決してどうでも良いというわけではなくそれはもう怒っておりますがここで書くことでもないよねということです)、独立書店まわりのことを中心に書いていきますね。
独立書店にまつわる2021年で個人的に気になった10大トピックス(順不同)
一昨年から、とある出版業界の飲み会で、その年の本屋周りのまとめみたいなことをラフに発表するようになったのですが、昨年末にもそれがあってですね。そこで発表したことそのままではあるのですが、加筆しつつ書いていきます。
1.棚貸し本屋の興隆
やはり、これが一番ですね。2020年末で把握していた数が11店だったのが知っているだけで今年は35店にまで増えていました(把握していないだけでもっと増えているかも)。
その中でも大きかったのは10月オープンの渋谷○○書店。クラウドファンディングのページで「後々は鎌倉○○書店みたいな展開もしていきたい」のようなことが書いてありますし、もっと有名になったら地方都市の駅ビルなどに増える可能性があります。
そのうち、私たちも渋谷に限らず「梅田◯◯書店」や「鎌倉◯◯書店」、「天神◯◯書店」といった全国各地に広がる偏愛ネットワークをつくっていくことも構想しています。
【渋谷駅直結】みんなで「新しいかたちの本屋さん」をつくりませんか?
色々な意見があるかとは思いますが僕としては棚貸し本屋が増えることは凄く良いことだと思っていて、それは人口も減り市場も縮小、どうしたって書店数自体は減っていく中で本屋(本のある場所)を増やすための手段として有望だと思うからです。
とはいえ、どんな物事にもどんなビジネスモデルにもメリットがあればデメリットもあるわけで、その点についてはちゃんと言っていかないとな、とも思うわけです。
2.冒険研究所書店
北極冒険家・荻田泰永さんによる本屋「冒険研究所書店」が5月に誕生しました。取材によるとやりたいのは普通の街の本屋(新刊も全体の3割から4割)みたいで、1月4日に取材した空葉堂書店さんもそうですが異業種からでも参入しやすくなっている証左になるかな、と。
昨年の独立書店年表にも書きましたが、本屋開業のノウハウが浸透したということはビジネスとして計算できるようになったということなんですよね。
つまり、本屋単体では無理でも、色々なビジネスとの組み合わせで成り立たせる(本屋をやることで他のビジネスにとっても相乗効果がある)ことが具体的に見えるわけです。
これは大きい。本屋専業はもちろんですが、異業種からの参入はまだまだ増えるような気がします。
3. 文喫 福岡天神
3月末開店。六本木の入場料制本屋「文喫 福岡天神」が二号店を開店しました。ここの成否によって、このやり方が広まるかどうかが決まるような気がします。
それにしても文喫のコピーは「本と出会うための本屋」なんですね。六本木店を初期の頃に取材したときに「書店員の選書スキルを価値付したい」みたいなことをおっしゃっていて、それをコピーライティング的に翻訳するとこうなるのかな、と。
4.fuzukue西荻窪
6月開店。本の読める店fuzukueがついに、店主の阿久津隆さんがいない店「fuzukue西荻窪」を作りましたね。まだ東京圏にしかないですが、ここが成功と思えるような形になったら、もしかしたら地方にもできるかもしれません。
「本を売る場所である本屋」ではなく「読書ができる場所」を価値として広めたfuzkueさんは本当にすごいよな、とあらためて思うわけです。
5.独立系書店の新刊予約また既刊本の《これからの》流通を語る討論会
10月開催。『東京の生活史』の子どもの文化普及協会から各独立書店への未配問題に端を発したzoomイベントですね。界隈では当時盛り上がっていたのでご存じの方も多いと思います。
いろいろトピックはありますが内沼晋太郎さんが事前に久禮亮太さんとも話していたという独立書店の連帯の話(インセクツの本屋特集でも触れていた)が僕の中では一番気になったところですね。実際問題、今後5年以内に必要な気がします。
6.久禮亮太さんがpebbles booksを退職してまたフリーに。
書店員の教育問題や上記5番の独立書店の連帯の話がどうなっていくのかというのも喫緊の課題な気がするんですよね(書店員についてはあまり分からないのでお話を聞いた限りの感触ですが)。
身軽になったであろう久禮さんがどう動くのかに期待です。
7.講談社とアマゾン、直接取引を開始
この問題については5番6番の話の進行と裏表な気がしますね。大きいところは大きいところで生き残ろうとしているわけです。それはそれとして僕としては独立書店とひとり/中小出版社のパイプができると良いように思うのですが最適解が分からない、というのが現状です。
それが独立書店の連帯と関わってくるとは思うのですが。
8.エトセトラブックス BOOKSHOP
1月開店。フェミニズム、というか本屋の社会性を感じさせる開店でした。ライトハウスやひるねこBOOKSもそうですが本屋と政治は来年以降トピックとしてあり得る気がします。何より本当に政治が大変なことになっていますし。
9.マルジナリア書店byよはく舎
1月開店。ひとり出版社による本屋の開店がまたひとつ。小鳥書房という前例もありますが、BSTでも借りてくれる出版社もいるし渋谷○○書店には百万年書房さんがいます。ひとり出版社が外に開かれた拠点を持つ意義が共有されはじめているかもしれないなと思い、入れました。
10.独立書店の興隆
ということで、10個目のトピックスはこちらです。独立書店年表に書いた2020年の開店数が35店だったのが今年の開店数は把握しているだけで51店に増えていました。棚貸し本屋だけでも15店は開店していますしもっと増えそうです。さらに棚貸し本屋から卒業したひと箱店主が自身で開業する例も増えそうです(BOOKSHOP TRAVELLERでも3店ほどおります)。今年もこの趨勢は続きそうですね。
***
いやー書いてみて思いましたが、「新刊書店」というビジネスモデルへの問いかけが多い感じがしますね。
「本の世界が続くことは重要ではあるが、大取次を中心としたいまのビジネスモデルは継続性の点が厳しく、であるならば他の方法論を試さなければいけない」
といったような問題意識が本の世界の人にはさらに差し迫ったものとなり、それが文喫や棚貸し本屋といった形になったのかと。さらに本屋の外の世界の人にはビジネスモデルの問題点がノウハウと共に浸透していったことで、本がある場所を運営するハードルが下がり、結果、異業種からの参入が増えたのかと。
(わかさ生活書店/わかさ生活薬店(2020年開業)、ページ薬局(2020年開業)、やず本や(2019年開業)もこの文脈だと思います。)
そういう感じの一年だったのかなと思いました。この流れがいつまで続くかわかりませんが少なくとも今年は続きそうです。