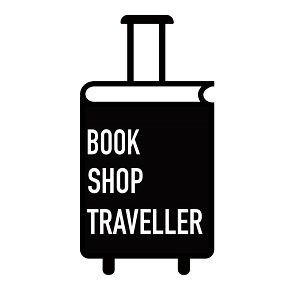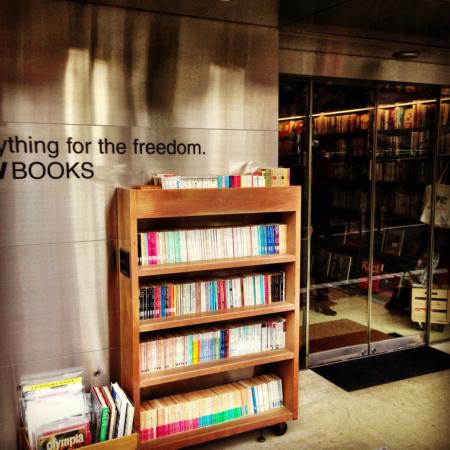台風の猛威がすごいですね。皆さんもよくよく注意してお過ごしください。僕は気圧で体調がけっこう大変です。さて、こんにちは、本屋ライターの和氣です。今日は前置きが長くなりますが、BookCellarでの八木書店注文は良いぞ!が言いたいことです。使いやすいし最高なのですよ。
- 書店と出版社を繋ぐ受発注Webシステム BookCellar
- 八木書店取次機能を2月から提供開始 ーオンライン受発注システムBookCellarに新機能ー
- 八木書店新刊取次部取り扱い出版社一覧(BookCellarページ下方にあり)
- 小取次については内沼晋太郎さんのこちらのnoteを参照
というわけで、それでは長い前置きからどうぞ。
***
BOOKSHOP TRAVELLERをはじめて4年。特に現店舗に移転してからは広くなったこともあり新刊をよく仕入れるようになった。どうやって、というといわゆる小取次からである。子どもの文化普及協会やトランスビュー、八木書店などの神田村、H.A.Bにツバメ出版流通などのことで、当店の場合、子どもの文化普及協会やトランスビュー、八木書店、H.A.Bに時おり直取引を加える形で仕入れを行っている。
こういった小取次に発注すれば(状況にもよるが)大抵の新刊は手に入るわけなのだが、ひとりや少人数で店をやっていると問題になるのが時間だ。やりたいこと・やらなくてはいけないことは無限にあるのに人出も時間も有限で片付けた先からあたらしいタスクが降って湧いてくる。
小売である以上、発注は非常に重要な仕事ではあるはずなのにそこにあまり時間が割けないこともあるだろう。もちろんプライベートな時間を充てればどうにかなるかもしれないが、人にはそれぞれの事情があり、であるならば効率化できる手間はできる限り効率化し、大事な仕事に力を振り向けられたほうが良いに決まっている。
そんなわけで、2018年のオープン当初に新刊を少しずつ仕入れ始めたときはウェブで発注できる子どもの文化普及協会を重宝していた。というのも、これは言い訳になるのだが、レイアウトやコミュニティに運営、イベント企画などの試行錯誤、さらにはライター仕事もあり、出版社と直接取引する時間も八木書店の店売に出向くことも難しい状況だったのだ。
なので、トランスビューが2019年にオンライン受発注システムBookCellarを採用したことは嬉しい驚きだった。これで品揃えをもっと充実させられると喜んだものである。
そこから1年経ち、2020年に移転してからは上記のように仕入れ点数を増やしたこと、さらに店舗運営が落ち着いてきたこともあり、八木書店に専用のエクセルで発注、毎週火曜日午前中に店売所に赴き仕入れてくるようになった。これにより、品揃えは以前よりだいぶ良くなった。というのも八木書店は仲間卸をしてくれるので着荷までの時間を問わなければ結果として流通しているほぼすべての本を手に入れることができるのだ。
とはいえ、書誌情報をウェブから拾ってエクセルに一点ずつ入力するのは思ったよりも手間がかかり、やはり八木書店に頼むよりは、オンライン上のカートに入れれば簡単に発注できる子どもの文化協会とトランスビューの本が自然と多めになっていた。
そんな状況下で、今年(2022年)2月に八木書店にもBookCellarに注文できるようになったことは本当に嬉しかったのである。
その分、掛率は78%程度と買切りであることを考えると厳しいのだが、文藝春秋や左右社など欲しかった出版社の本を一冊から仕入れられる。それが、ISBNコードを入力するだけで簡単に発注できるだなんて! 八木書店への発注量が増えたことは言うまでもない。
さて、ここでようやく本題である。つまり、同じようなことがもしかしたら全国の独立書店でも起こっているかもしれないと思ったので、八木書店の新刊取次部の方に話を聞いてみることにしたのだ。以下はインタビューの内容をまとめたものだ。
01.jpg)
02.jpg)
***
BookCellarをはじめることになったキッカケは?
発端は社内的な事情です。業務効率化の一環として注文サイトの導入ということがありました。BookCellarの存在は一利用社として知っていましたが、とあるイベントをキッカケにして運営会社である㈱とうこう・あい様に相談してみることになりました。
その中で様々な懸念点はありましたが、ここで弊社が参加してもしなくても世の中の直取引の流れが変わるわけでもなし、まずはお取引先様へのサービスの増強を目指すことにしました。
ただし「やぶれかぶれ」ではなく、直取引もメリットだけではないと思っています。見た目のマージンは増えても出荷の手間や送料、与信管理など出版社・書店双方にとって細かなルーティンが発生し、皆が皆、直取引に対応しきれないですし、それを請け負う取次には存在価値はまだ十分あるとも思っていました。
また、弊社は出版社としてもBookCellarを利用していますが、学術書版元なのでBookCellarでも書店外商部様からのご注文が多いです。専門書出版社ほど、BookCellarに参加すべきではないかと思います。
BookCellarをはじめたことで取引先は増えましたか?増えたとすれば
どれくらいですか?
新規のお取引先は増えました。運用開始は今年の2月からですが、ありがたいことに、新規に取引口座を開設させていただいた店舗様は70件くらい(2022年8月現在)あります。また、そのほとんどがバーゲンブックでのお取引申請も同時にしてくださっています。
(八木書店は、発売して一定期間が経った本のうち出版社が価格拘束を外して再流通させる判断をした在庫(=自由価格本。バーゲンブック。値引きして販売できる新本)の専門問屋でもある。詳しくはこちら)
一方で、各種契約書の締結を煩雑と感じられてしまうのか、口座開設に至らなかったケースもあります。ですが、弊社としては、単に「注文を受けて出荷する」という出荷倉庫ではなく、お互いに常に相談や提案がしあえる関係でありたいと考えており、もろもろの手続きもその一環でお願いしている次第です。
03.jpg)
05b.jpg)
BookCellar経由の注文と従来どおりの注文方法(FAXやエクセル、電話)
での注文とで、注文内容の傾向は違いますか?違うとしたらどう違いますか?
同じ書店様でご注文の傾向が極端に変わったということはなさそうです。ただし、未刊商品のご予約は入りやすくなったと思います。というのも、BookCellarはopenBDから書誌データを取得しており、近刊情報もそのデータベースに入っているからです(BookCellar経由で予約注文ができる 筆者注)。
刊行前に自店向きの本の情報が取ることができ、お客様に案内して客注が取れるというのは大きいと思います。特に弊社は書店様とは基本的に買い切りでのお取引ですので、仕入れてから店頭に並べて購入を待つだけでなく、刊行前に客注がとれる近刊情報は利用価値が高いと思います。
新刊はリアル書店で先行販売されることはあっても、ネット書店が先ということはほぼありませんので、未刊タイトルは同じ土俵で商いができる商材です。もちろん取次の立場では出版社様の方で出荷調整が入ってしまうとどうしようもないのですが、ほとんどの場合、弊社には満数出荷いただけています。
06.jpg)
07.jpg)
トランスビューや直取引の入力方法とは別に、カート画面下部に専用の注文欄がある。
八木書店で直接取扱いのない出版社の銘柄の調達を要請できる「リクエスト機能」もあり。
独立書店と呼ばれるような小さな本屋が増えていますが、取次の立場からはどのように感じられますでしょうか?
長く営業を続けてこられた街の本屋さんが泣く泣く閉店を選択されていくなか、それでも本屋をやりたい、本を置く場所を自分の手で維持したいと考える方が多いのは、とても心強いです。
出版社はリアル店の減少、紙の本の売上減を、電子書籍や版権、他メディアでの展開など、商材、業態を変えて、この状況に対抗していく余地がありますが、取次は基本的に紙の本以外に商材を持ちませんので。
『街灯りとしての本屋』(雷鳥社)という本がありますが、「街灯り」を維持するための良きパートナーになれるよう私どもも日々努力したいと思います。
ちなみに、多くの独立書店、また本も併売される雑貨店は、大手取次様と契約をされていない結果、JPRO同様にJPO(日本出版インフラセンター)が運営する「書店共有マスタ」から漏れてしまっているそうです。そのため、多くの独立書店・雑貨店が統計からもれており、独立書店様の存在感が高まるなか、BookCellarでどうにか集約していただいて業界団体に対して意見交換していくのもよいかもしれません。すみません、これは勝手な提案です。
今後実現したいこと(BookCellarを通してでも通さなくてでもOKです)はなんでしょうか?
お取引書店様に取次経由でもいかにマージンを確保いただくかが課題です。取次としての調達力の向上ですね。
出版社にとって出たばかりの新刊を売り伸ばすこと以上に難しく、大切なのが既刊書の販売です。評価が定まっている定番書の継続的な販売はもちろんのこと、刊行後しばらく経過して注文が停滞している既刊を、いかに掘り起こし、販売につなげるかは版元営業の課題で、重要だとは思いつつ新刊の営業に追われてなかなか出来ないということがあります。
弊社の場合、グループとして単独で出版社、取次(新刊・自由価格本)、小売(古書店・外商)、催事会社をもっているのが情報・ノウハウの蓄積という点が強みですのでお取引書店様との連携によって既刊の売り伸ばしについて代行できれば、新たな展開が待っているように思います。
ひとりや少数でこれから新刊を仕入れる/仕入れたいと考えている人へのアドバイスをお願いします。
すでにたくさんの先達がおられますので、インディペンデントで開業運営されるにあたっては、いろいろ見学されるのが良いと思います。
営業にあたっては、コンスタントに売上を計上するために、客単価を上げる、ニッチな品揃えにして専門店になる(神保町の古書店は専門店の集まりです)、いろいろご自身にあった戦略を練られるのがよいと思いますが、「仕入れてから売る」に加えて「注文を取ってから仕入れる」も検討していただけるとよいかもしれません。
その方法のひとつが、さきほどの未刊商品の注文取りです。あとは既刊の客注。新興の書店様であまりお見かけしない「外商」という販売方法も頭の片隅に置いておいていただいてもよいかもしれません。
最近、移動型本屋さんも増えていますが、読者のもとに直接おもむく、見計らいをする(図書館などで一定期間本を展示し現物選書してもらう)、チラシ・メールなどで注文取りをおこなう(ちなみにこれらは版元営業として普段私がおこなっていることです笑)などは部分的にでも取り入れられると「受注発注」の実現や固定のお客様をもつ契機にもなるかと思います。
実際、長く弊社の店売を毎週ご利用いただいている書店様のなかには、店舗はもたれず、複数の個人読者の方に注文取りをされてから、神田村の各取次から調達をされている書店様がおられます。
粗利確保という観点では、弊社取り扱いの自由価格本(バーゲンブック・アウトレットブック)も常設、ワゴン販売、催事など展開方法はいろいろありますが、採用をご検討いただければと思います。
最後に送料一覧
| 発送先地域 | 料金 |
| 北海道 | 700円+税 |
| 東北 | 600円+税 |
| 関東 | 500円+税 |
| 東海・中部・北陸 | 600円+税 |
| 近畿 | 600円+税 |
| 中国 | 700円+税 |
| 四国 | 700円+税 |
| 九州 | 800円+税 |
| 沖縄本島 | 実費 |
| 離島 | 実費 |
***
以上です。いや、ほんと、八木書店さんは送品一回あたり何個口でも送料が一律ですし、東京近郊じゃなくてもおすすめなのですよ! これから本屋を開く方も、すでに開いている方も、まだご利用されていないようでしたら、ぜひBookCellarと八木書店のご利用をオススメしたいワタクシなのであります!